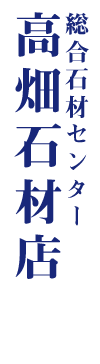お知らせ
初めてお墓を建てる方へ
お墓を建てることになったという方や建てることを考えている方も少なくないでしょう。とはいえ、特に初めてという方はお墓の建て方にどのようなものがあり、どこに注意すればよいのかわからないのではないかと思います。そこで、今回は、お墓の建て方をご紹介いたします。
お墓の建て方について
お墓といえば、年に何度か定期的にお墓参りをする場所やすでに亡くなったご先祖様が眠っている場所といったイメージがあるでしょう。
そのお墓を新しく建てるということになった方もいれば、現在建てることを考えている方も多いのではないでしょうか。
中には、あらかじめ元気なうちにお墓を建てておきたいという方もいるでしょう。
しかし、お墓を建てるといっても、どのような建て方があり、どのような点に注意すればよいのかがわからないという場合もあると思います。
いつ頃お墓を建てればいいのか
特に決まりがあるわけではない
実はお墓を建てる時期については法律においても、また仏教の教えの中でもきちんと決まっていたり、明記されていたりしているわけではありません。
言い換えれば、「この時期でなければいけない」というような決まりがあるものではないということです。
そのため、建てる時期としては、ご自身が元気なうちであっても、亡くなった直後であっても、あるいは事情を考慮して亡くなってから1年以上経過した後でも構わないということになります。
一般的によくお墓が建てられている時期
一方で、世間一般の傾向として、ある程度お墓が建てられることが多い時期というものがあります。
そして、お墓が建てられることが多い時期は、すでにお墓を用意した方と葬儀の後にお墓を建てた方とによって違いが見られます。
前もってお墓を用意したという方の場合は、故人の四十九日法要が終わった時点で納骨ができるように生前から建てていることが多いです。
なお、生前に建てたお墓は「寿陵」と呼ばれ、縁起のよいお墓とされています。
また、縁起の良し悪しだけでなく、相続税対策にもなるということで将来のご家族の負担を減らすために建てる方も多いそうです。
一方で、お墓を葬儀の後に建てるという方の場合は、四十九日法要以後の完成を見越して、納骨の時期が一周忌や三周忌の節目となるように建てることが多いです。
実際にお墓を建てるとなると、石材店に依頼してから数ヶ月ほどの時間が必要となってしまうため、故人の四十九日だけでなく百か日法要にも間に合わないためです。
お墓をどこに建てるのかを決める
お墓の建て方を考える要素として、お墓を建てる場所もまた重要となります。
お墓を建てる場所といえば、墓地や霊園が考えられそうですが、このほかにもあり得るのかどうかという問題も含めて考えていきましょう。
墓地の形態
まず、お墓を建てる場所についてですが、原則として墓地や霊園に建てることとなっています。
なぜなら、墓地について定めた「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法、墓埋法)」の第4条で決められており、「墓地以外の区域」ではお墓を建てることが禁止されているためです。
そして、お墓を建てるための墓地や霊園の形態には、寺院墓地・公営霊園・民間霊園の3種類があります。
・寺院墓地
寺院墓地とはお寺が管理している墓地のことです。
基本的にはその寺院の檀家(寺院を経済面で支える家のこと)のみが使用することができます。
寺院墓地のメリットとして、単にお墓や故人の供養のことだけでなく、身内の方の葬儀のことなどに関しても相談に乗ってもらうことができるという点や墓地自体がアクセスの良いところにあるという点、さらに供養などが手厚いという点が挙げられます。
その一方でデメリットとして、特定の宗派以外の方は利用できないという点や檀家になることが利用の前提条件となっている点などが挙げられます。
・公営霊園
公営霊園は市町村などの地方自治体が運営している霊園の事です。
地方自治体による運営であることから、運営の元手として税金が投入されています。
公営霊園のメリットとして、税金で運営されているため、自治体が財政破たんしない限りは霊園そのものが潰れないという点や、管理費や永代使用料(お墓の土地代のこと)が安く設定されているという点、国籍や宗教・宗派に関係なく利用できる点などが挙げられます。
反対にデメリットとして、人気のある霊園の場合は応募が殺到しやすいという点や生前購入が難しい点、管理費が安いぶん、掃除用具が備えられていない場合もあるといった点があります。
・民間霊園
民間霊園は石材店などの民間企業や公益法人などが運営する霊園のことです。
中には複数の石材店が運営団体を立ち上げて管理している場合もあります。
メリットとしては、公営霊園の場合と同じく国籍や宗教・宗派に関係なく利用できるところが多い点や墓石の形やデザインを選ぶことができる場合が多い点、さらに施設や交通手段が充実している傾向にあるという点が挙げられます。
一方でデメリットとして、施設を充実させているぶん、永代使用料や管理費が高い場合がある点や霊園によってはお墓を建てる際に利用できる石材店があらかじめ決まっている場合もあるという点が挙げられます。
お墓の立地
お墓の建て方を見るうえで場所のことを考える際にもう1つ見逃せない点が、お墓の立地についてです。
墓地の立地はお墓を建てる際にそのための土地区画に対して発生する永代使用料に大きく影響してくるためです。
まず、アクセスが良くお墓参りに通いやすいところや墓地の周辺環境の良いところなどは人気が高く、永代使用料も高くなりがちです。
加えて、人気の高さは空き区画が早めになくなりやすいことも意味します。
さらに、墓地が立地している地域の地価も見逃すことはできません。
都市部であるほど高く、地方に行くほど安くなるというのが大まかな傾向で、こちらもそのまま永代使用料の金額に影響します。
お墓を建てる際に必要なこと
お墓を建て方において、実際にお墓を建てる墓地や石材店の選定や、墓石の検討といったことも重要ですが、お墓を建てる際にやっておく必要のあることもまた欠かせない要素になります。
ここでは、故人のご遺体の火葬を行ったことを示す火葬証明書の提出や、お墓の建立の最後の仕上げである開眼供養についてご紹介いたします。
火葬証明書を提出する
火葬証明書とは、故人のご遺体を葬儀の際に火葬したことを証明する書類のことで、火葬が終了した段階で火葬場が発行するものです。
似たような書類に「火葬許可証」というものがありますが、これは故人のご遺体を火葬場で火葬することを許可するための書類であるうえ、火葬後は埋葬許可証となる書類のことを指します。
この火葬証明書は納骨の際に埋葬許可証とともに提出されるもので、埋葬許可証とともに納骨の際に不可欠な書類です。
特に故人が死亡してから5年以上経っている場合、火葬証明書はすでにご遺体を火葬したことを証明するために必要となります。
開眼供養を行う
めでたくお墓そのものが完成したとしても、実はそれだけではお墓はただの石材の塊にすぎません。
お墓がお墓になるには、最後の仕上げである開眼供養を行う必要があります。
開眼供養とは、お墓にご先祖様の魂を入れるための儀式のことで、この儀式によって初めてお墓は故人が安らかに眠る場としての機能を持つことになります。
開眼供養を行うには、読経を行う僧侶への依頼のほか、実際にカロートへの納骨作業を担当する石材店への依頼といった下準備が必要となります。
お墓を建てるとなると、人生の中の大きな買い物の1つといわれるだけあって、さまざまな点について情報を集めたり、検討したりする必要があるといえます。
長期的に使うものであるため、お墓との将来の付き合い方についても視野に入れる必要もあります。
そのため、お寺や石材店などとよく相談しつつ、多くの情報をもとによく検討して、理想通りに建てられるように準備をしていくことが、お墓の建てる上でのコツといえるでしょう。
兵庫県で墓石に関することなら総合石材センター 髙畑石材店にお任せ下さい。
会社名:総合石材センター 髙畑石材店
住所:〒669-5211 兵庫県朝来市和田山町平野374-1
TEL:079-672-2535(工場) 079-672-5358(展示場)
FAX:079-672-1100
営業時間:8:00~18:00 年中無休
業務内容:墓石製造・販売・設計・施工、石材彫刻品製造・販売